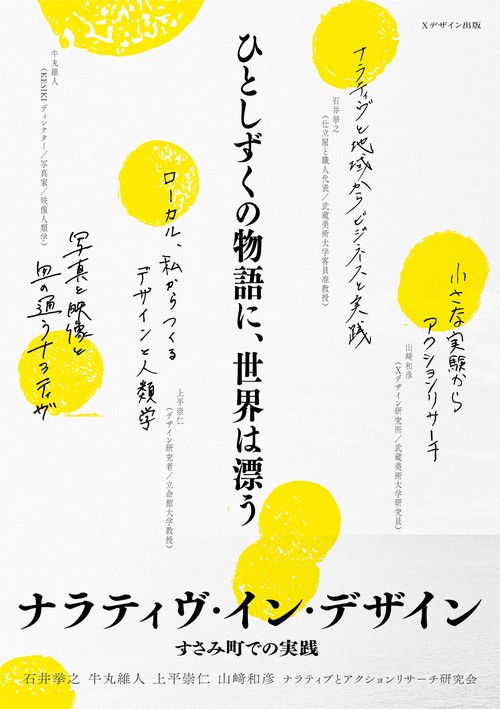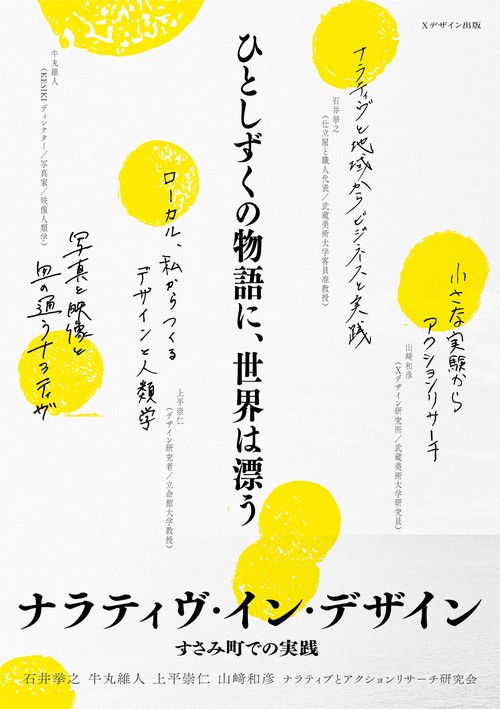日に日に世界が広くなるデザインという沃野。その広がりに灯る、ナラティヴという小さな光。それは社会の捉え方でもあり、物事の考え方でもあり、問題への取り組み方でもあります。その軸に流れるのは、コモンセンスのような最大公約数が重んじられる世の中からこぼれていきがちな多様かつ小さな声を、丹念に、丁寧に、掬い上げようとするアティチュード。語りや物語と表されることもありますが、帯に短し襷に長し。では、何だろう?というところから探究が始まります。でも「人は、一人ひとり違うんだ」という根源的な事実に向き合いながら、人間という生き物の豊かさを実直に捉えようとする姿勢であるということは確かで、デザインと人類学が近づいている昨今、とても面白いのです。
第1章「ひとしずくの物語」では、識者4人が各々の知見でナラティヴ観をつまびらかにします。解釈によって姿が変わるナラティヴが何者であるのか、各々の光で照らしていきます。ただナラティヴについて語るだけでなく、この本では和歌山県すさみ町という人口3,000人台、ほぼ本州最南端の小さな町を舞台にして語り合っていきます。一つひとつ違う固有の声に耳を傾ける場として、そんな声について共に考えや試みを重ねる場として、実際に幾度となく筆者たちが訪れた町。人が少ないからこそ建前や虚栄の必要もなく、海・山・川と自然豊かな風土が育んだ一人ひとり違う声が気さくに本音で語られる、ナラティヴを探索するのに楽しい土地です。第2章「すさみの物語」では、そんな楽しさに共鳴するメンバーが町を訪ねて実践した色とりどりの探求を言葉へと昇華させ形にしています。前章の4人はデザインや人類学をフィールドとする探究者としてある意味近しいですが、当章にはバックグラウンドが多彩に異なる、価値観も視点も違った20人を超えるさまざまな個性が、言葉をともしびに集まっています。みな解釈も実践も違うからこそ、その軌跡は読み通していくほどに多彩な光で象られ、ナラティヴというものの実像がありありと浮かび上がってきます。第3章「世界は漂う」は、この本の物語がどのように生まれ、そしてどう世界は漂うことになるのだろう、という問いに答えるべく、4人の識者による対話が語られます。読み終えた時には、きっとこんな想いと出会うことでしょう。世界は単純でも一様でもなく、瑠璃色のようにさまざまな輝きに満ちた美しさを持っているからこそ、その一つひとつの輝きを大切に受け止め、素直な眼差しで見つめることが大事なのだ、と。