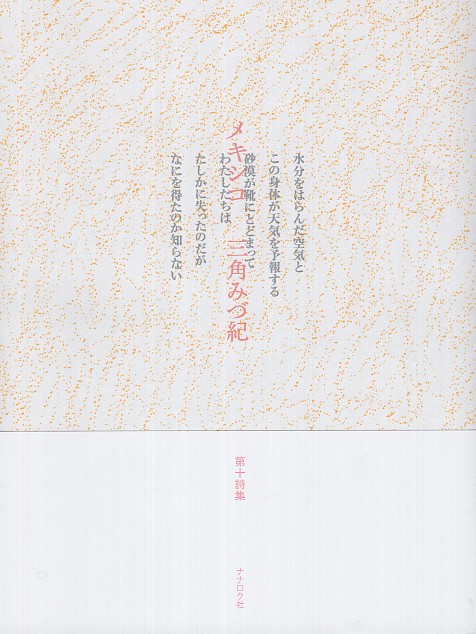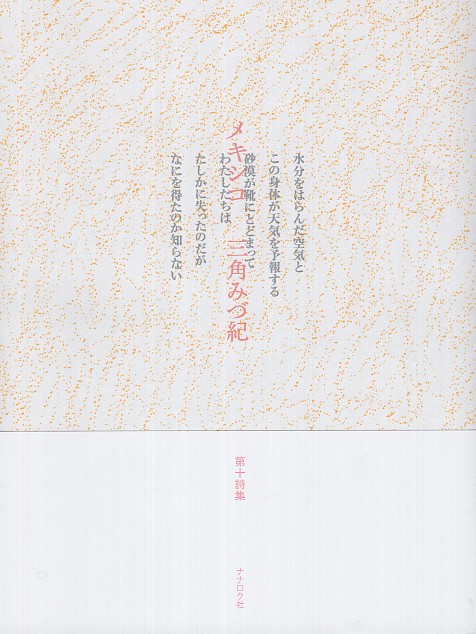中原中也賞、萩原朔太郎賞の受賞詩人、三角みづ紀の10冊目の詩集。
2023年と2024年、2度のメキシコでの滞在中に書かれた37篇の詩と17篇のエッセイを収録しました。
知らない土地で言葉を綴る行為は、生まれかわるための行為だとおもう。
過去の自分を模倣するように表現することが、わたしにとってはもっともおそろしいことだ。
なので、何度でも手放して、何度でも死ぬ必要があった。
—「二〇二四年七月初旬、メキシコシティにて」より
一冊ごとにあたらしい自分と出会い、詩を書き続けてきた三角みづ紀のメキシコでの日々。
「詩の第一行みたいに、そこにある」と、詩人が捕まえた世界の美しさにぜひふれてください。
●あとがきより
=====
二〇二三年の九月より三カ月、二〇二四年の三月末より四カ月。わたしはメキシコにいた。一回目の滞在ではエッセイをたくさん書いて、二回目の滞在では詩をたくさん書いた。(中略)
ノートをひらき、線を引く。デッサンをするように、大切な瞬間をとらえて描いていく。わたしにとって入口は同じだった。質感や感情のかたちによって、余白の多い詩になったり、物語をはらんだエッセイになったりする。
本著は十冊目の詩集であり、わたしのメキシコの日々そのものでもある。
=====
●詩「乾季のおわり」より
=====
水分をはらんだ空気と
この身体が天気を予報する
砂漠が靴にとどまって
わたしたちは
たしかに失ったのだが
なにを得たのか知らない
=====