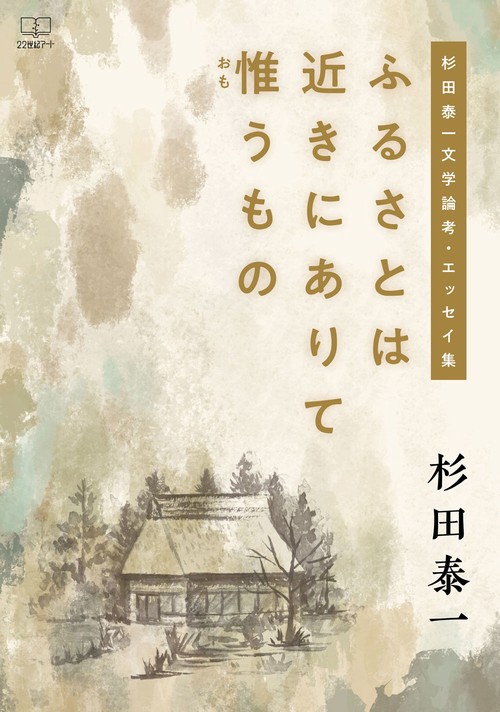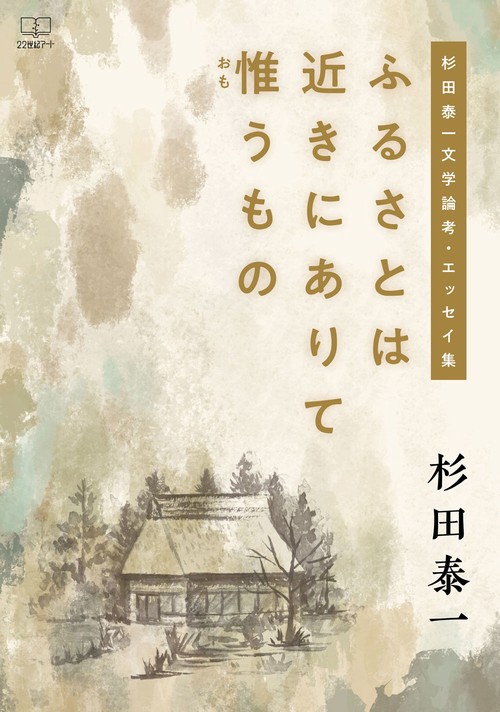ふるさとは遠きにありて思ふもの/そして悲しくうたふもの
そう歌った詩人・室生犀星にとって、これはたんなる望郷の詩ではなかった。そこには、不義の子であった詩人が、故郷の現実に絶望し、復讐心さえ持ちながらも、故郷を完全に切り捨てることができない魂の苦悩がひびき渡っている。サルトル、キルケゴール、ヤスパース、ハイデッガーなど知の巨人たちが提起した問題に目を向けながら、詩人にとって故郷とは何であったのか、われわれにとって故郷とは何なのかを鋭く考察した「人間、この病めるもの」、萩原朔太郎の一篇の詩を題材に、詩人の中での故郷の位置づけの探究を通じて、我われにとっての故郷の意味を問う「故郷とは 萩原朔太郎」など、本書は放送大学の客員教授時代を含め、著者がこれまで発表した論稿や小文、講演・セミナー等の内容を加筆・修正して、まとめたものである。都会化によって便利さだけが優先され、ふるさと的なものの喪失を招いている現代において、私たちが切り捨てながらも心の底のどこかで渇望する「何ものか」を炙り出す一書として、示唆に富む内容となっている。