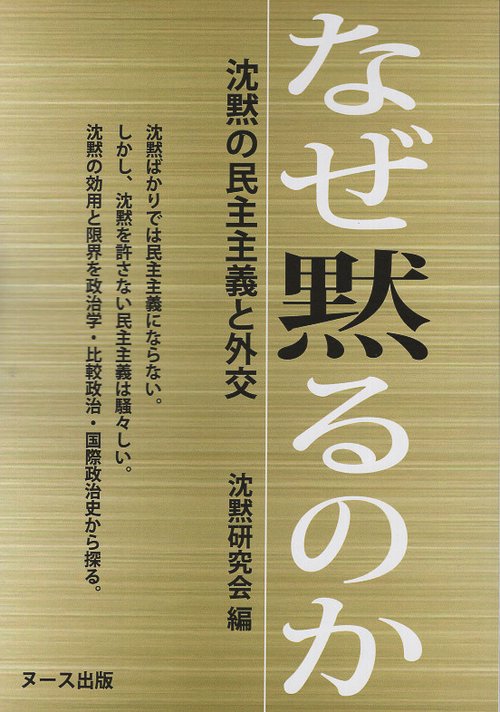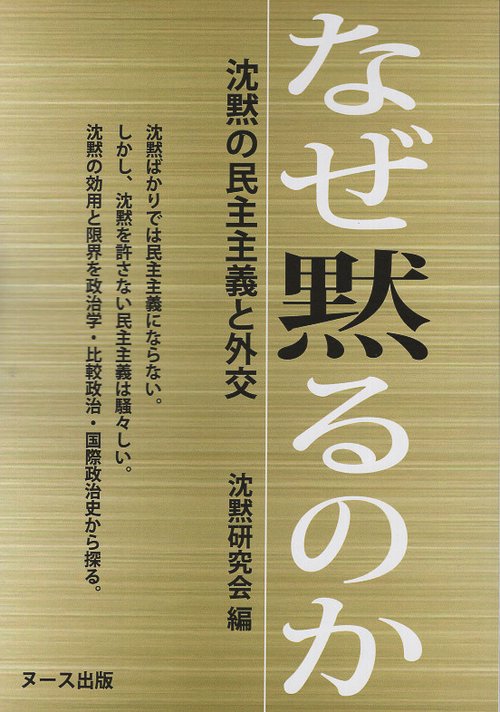沈黙ばかりでは民主主義にならない。
しかし、沈黙を許さない民主主義は騒々しい。
沈黙の効用と限界を政治学・比較政治・国際政治史から探る。
時に、沈黙ほど雄弁な表現はない。それは沈黙がイエスであるにせよノーであるにせよ、解釈を拡げられる表現だからである。舞台では「間」の取り方として重宝されている。
それでもこの掴みにくい難題に本書が挑戦しようとしているのは、民主主義を謳う国や世界において、議員の発言が批判され、時には揶揄されるのに比して、だんまりを決め込んだり沈黙ばかりでは民主主義は進まないためである。逆に、インタビュアーに囲まれた人たちにとって、その身を守る方法は沈黙である。沈黙に不寛容な社会も未成熟で喧噪的で、居心地がよいとは思えない。
本書は、政治学、比較政治、国際政治、外交史の立場から沈黙の理論と事例にアプローチする。一般に学者は、議事録、発言録、回顧録に始まり、オーラル・ヒストリーやインタビュー手法にいたるまで、発話された言語を重視する。同時に、一次史料や二次資料をふまえ、文字情報を大切にする。しかし沈黙ほど、それらの方法の届かない状況はない。沈黙は、時に無視され、なかったことにされ、否定される。それでもわたしたちの日常生活から政治世界、国際政治にいたるまで沈黙が確認されるのは、発話と同じように沈黙も主体の感情や考えを示す手段であることの証左に他ならないためである。その感情や考えを他者がどれほどくみ取れるのか。それを他者に任せるのが沈黙である。
本書では、沈黙の先行研究をふまえ、第一章で沈黙の定義と分類を行う。沈黙には個人の沈黙だけでなく、集合的な沈黙も含めるべきである。沈黙は、国内の政策過程において、政策決定者にとっては不都合なときに、政治参加をする側からすれば脱力的なときにおこりやすい。政治的疎外や投票棄権行動、特定理念への合意を政治的沈黙と解し、ドイツの民主政治を沈黙の政治の観点から分析するのが第二章である。続いて第三章では、日本の選挙参加を事例に沈黙の表出をとらえる。第四章では環境政策の転換後の政策の沈黙に鋭く切り込む。
言行不一致が多い国際政治では as if game のもとで、不都合な時に沈黙が多用される。第五章では、東西欧州の安全保障の対話の場として始まったCSCEでみられる「暗黙の了解」に接近する。沈黙が外交で現れる場合に、その意味を測る一つの方法は時間である。沈黙の長短に着目して第六章ではモンゴル・日本のEPA交渉を追う。第七章では、対立する国の間にあって難しい対応を迫られた日本の沈黙を1960年代の外交史料をひもといて明らかにする。
沈黙が方々にある一方で、他方では沈黙を破ること(破黙)や沈黙を奪うこともある。その後、沈黙に戻ることもまた容易である。それが可能なのが民主主義制度の下の社会の特徴である。本書を通じて沈黙への多様なアプローチを紹介できればと願う。
(本書「はしがき」より)